エクアドル国歌をめぐる試みの中には、1865年にアルゼンチン人フアン・ホセ・アジェンデ(Juan José Allende)によって提案された作曲案も含まれていたが、これは実現には至らなかった。
国家のアイデンティティの構築には、多くの場合、集団的記憶や自由の理想を凝縮した象徴が伴う。エクアドルにおいても、国歌の制定に至るまでの道のりは長く、困難を極め、政治的・文化的な議論に満ちていた。共和国の黎明期における最初の試みから、無名の提案やイデオロギー色の強い詩を経て、フアン・レオン・メラ(Juan León Mera)の詞とアントニオ・ネウマネ(Antonio Neumane)の曲によって現在の形に落ち着くまで、エクアドルは幾度となく失敗と論争を繰り返しながら、自国の象徴となる国歌を模索してきたのである。
そして1948年、この愛国の歌はついに、無形の国家的象徴として公式に認められることとなった。
最初の試みは、1830年の共和国成立後に始まった。当時の大統領フアン・ホセ・フローレス(Juan José Flores)は、副大統領であり、グアヤキル出身の著名な詩人でもあったホセ・ホアキン・デ・オルメド(José Joaquín de Olmedo)に対し、新たに誕生した国家にふさわしい歌の作詞を依頼した。オルメドは「国民の歌(Canción Nacional)」を作詞し、合唱と四つの節から構成されるその詩において、独立の偉業が称えられ、ピチンチャが自由の舞台として描かれていた。しかしながら、この作品は楽曲化されることなく、公式に採用されることもなかった。その歴史的意義は、国歌としての最初の表現であるという点にあるが、当時の政治的関係者の枠を超えて広く普及することはなかった。
1833年には、政府機関紙『ガセタ・デル・ゴビエルノ(Gaceta del Gobierno)』において、「エクアドルの歌(Canción Ecuatoriana)」と題された匿名の作品が掲載された。この詩は六つの節から成り、共和国の誕生を描いた長編詩であったが、公的な支持も著者の名もなく、注目を集めることもないまま、記録に残るのみとなった。
さらに五年後、フローレス自身が『ラ・エルビラにおける隠遁中のフローレス将軍の詩(Poesías del General Flores en su retiro de La Elvira)』という小冊子の中で、新たな「国民の歌」を発表した。そこでは、「独立か死か」という熱烈な文句と、共和主義の主権を高らかに称える詩句が盛り込まれていた。この提案は、それまでのものよりは広く知られるようになったものの、やはり国歌としての地位を確立するには至らなかった。
これら初期の作品はいずれも、国民的な支持を欠いており、また当時の政情不安の影響もあって、国家の象徴として定着するには至らなかったのである。
1860年代、ガブリエル・ガルシア・モレノ(Gabriel García Moreno)政権下において、国歌制定のプロジェクトは再び勢いを得た。内戦後に国家を再統一した同大統領は、国の象徴を確立することを目指し、三色旗(バンデラ・トリコロール)と大コロンビア共和国の国章(エスクド・グラン・コロンビアノ)を復活させるとともに、国歌の制定も奨励した。このような背景のもと、1865年にはアルゼンチンの音楽家フアン・ホセ・アジェンデが、ホセ・ホアキン・デ・オルメド(José Joaquín de Olmedo)の詩に曲をつける試みを行ったが、国会はこの提案を採用しなかった。
しかし同年、国歌制定における決定的な転機が訪れた。上院議長ニコラス・エスピノサ(Nicolás Espinosa)が、アンバト出身の詩人であり政治家でもあったフアン・レオン・メラに新たな歌詞の執筆を依頼したのである。
1865年11月15日の夜、メラは一気に、現在「国歌(Himno Nacional)」として知られる詩を書き上げた。この詩は、スペイン=南アメリカ戦争の最中、太平洋に現れたスペイン艦隊の脅威を背景にして生まれたものであり、植民地支配への反抗と、1809年および1822年の独立運動における英雄たちへの賛辞を高らかに歌い上げている。その内容は、旧宗主国スペインに対する激しい反感を表現しており、「血に飢えた怪物(monstruo sangriento)」や「スペインの残忍さ(fiereza española)」といった表現を用いて、独立の記憶を呼び起こし、戦う精神を鼓舞しようとする意図が込められていた。
国会はこの歌詞を承認し、フランス出身でグアヤキルに居住していた音楽家アントニオ・ノイマネ(Antonio Neumane)に作曲を依頼した。ノイマネは1866年に楽譜を完成させ、1870年8月10日、キトにて自らの指揮で国歌の初演が行われた。この日を境に、エクアドルの国歌は事実上の国民歌として受け入れられるようになったが、法的にその地位が保障されるまでには至っていなかった。
時が経つにつれ、フアン・レオン・メラの歌詞は論争の的となった。その内容がスペインに対してあまりにも厳しいものであったため、エクアドルがイベリア半島(スペイン)との外交関係を正常化しようとしていた時代背景においては、不都合なものと見なされ始めたのである。メラ自身は、歌詞の改変に対して断固反対の立場を貫いた。一部の勢力がその表現を和らげるよう求めた際には、「国歌の歌詞は手形(letra de cambio)ではないから変更しない」と皮肉を込めて述べた。しかし、批判の声は依然としてやまなかった。
20世紀初頭、元大統領ルイス・コルデロ(Luis Cordero)は、「母なる祖国(スペイン)」に対する怨念を排した新たな国歌を制定するため、詩文コンテストの開催を提案した。これに続いて、1913年には作家であり外交官でもあるグアヤキル出身のビクトル・マヌエル・レンドン(Víctor Manuel Rendón)が、マドリードにて『エクアドルの新国歌(Nuevo Himno del Ecuador)』を発表した。レンドンの歌詞は和解を基調としたものであり、従来の対立的な姿勢を「母なるスペイン」との親和的な関係へと転換しようとする内容であった。彼は自作の歌詞を国会に採用させようと試みたが、この動議は最終的に却下された。
議論は完全には沈静化しなかった。1924年、国会はエクアドル言語アカデミー(Academia Ecuatoriana de la Lengua)に対し、国歌の見直しを委嘱した。アカデミーは公式な歌詞の修正は行わないと決定したが、儀礼的な行事においては、スペインに対して最も攻撃的とされる第一連を省略し、コーラスと第二連のみを歌うことを推奨した。この慣行は次第に定着し、現在に至るまで公式の場における国歌の演奏方法として受け継がれている。
メラの詩とヌーマネ(Antonio Neumane)の旋律が国民の間に深く根付いていたため、いかなる改正の試みも国歌の差し替えには至らなかった。
最終的に1947年、当時の教育大臣はアウレリオ・エスピノサ・ポリト(Aurelio Espinosa Pólit)と、詩人メラの息子フアン・レオン・メラ・イトゥラルデ(Juan León Mera Iturralde)を委員長とする委員会を設立し、過去のすべてのバージョンと提案を検討させた。その報告書は、国歌を公式かつ不可侵のものとして認定するよう勧告した。
この勧告を国会は受け入れ、1948年9月29日、メラとヌーマネの作品をエクアドルの正式な国歌として制定する法令を可決した。同年11月8日にはガロ・プラサ(Galo Plaza)大統領がこれに署名し、11月23日付で官報(Registro Oficial)にて公布されたことにより、100年以上続いた不確実性の時代に終止符が打たれた。
それ以来、エクアドル国歌は無形文化遺産として保護され、国家の不変の象徴として位置付けられている。対立の時代に生まれたとはいえ、この国歌は今や過去の論争を超越する国民的象徴へと昇華された。その歩みは、記憶と外交、アイデンティティと政治的利害との緊張関係を映し出しており、国民的象徴とは闘争、合意、そして妥協の産物であることを示している。
エクアドルの国歌についてはこちらを参照のこと。
参考資料:
1. De canciones dispersas a símbolo patrio: la larga historia del Himno Nacional del Ecuador


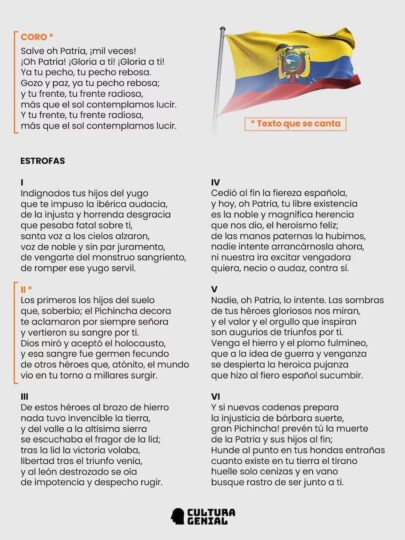
No Comments