1980年代初頭、センデロ・ルミノソ(Sendero Luminoso)がペルー国家に対して武装闘争を開始した際、アルト・アンデス地域に位置するワリャ(Hualla)の共同体は、その最初の「解放区(zonas liberadas)」の一つとなった。だがワリャはすぐに、反政府勢力の支援拠点となったことにより、極めて大きな代償を払うこととなった。ワリャは、ペルーの中でも最も多くの人々が親族の遺体、またはその残骸の返還を待っている場所の一つである。ここには、行方不明者の遺族である74家族が暮らしており、未亡人や孤児たちは、喪失を乗り越えることができず、今もなお答えを求めて探し続けている。
アルト・アンデス地域は、先住民文化が強く根付いている場所でもあり、インカ帝国の中心地でもあった。現在でもケチュアやアイマラなどの先住民が多く住んでおり、伝統的な農業や手工芸が営まれている。棚田(Terrace)など、高地に適応した農業技術が発展している地域でもある。20世紀後半から21世紀初頭にかけて、アルト・アンデス地域は武装勢力の活動が目立った。センデロ・ルミノソは、ペルーのアルト・アンデス地域で活動を強化し、多くの戦闘が行われた。この地域は政治的に非常に重要な場所でもあった。
暴力の終結から30年後、この共同体は国内武力紛争(conflicto armado interno)によって犠牲となった人々を追悼する記憶の空間(メモリアルスペース)を開設した。そして住民たちは、いまだ癒えぬ痛みを伴う過去について、長く続いた沈黙を破ろうとしている。ルイス・シントラ(Luis Cintora)監督は「罪なき罰のゆくえ(Este fue nuestro castigo)」を通じ、その様子を記録する。監督はドキュメンタリーは、「しばしばその時代の現実や、現在にも関わりを持ちうる過去の出来事を映し出す使命を担っている」と語る。
赤い地域
サン・ペドロ・デ・ワリャ(San Pedro de Hualla)は、アヤクチョ(Ayacucho)の南部、ビクトル・ファハルド(Víctor Fajardo)県に位置する町である。ワリャは、国内武力紛争の影響が今も続いている地域である。この地では、戦争で命を失った人々や行方不明者への哀悼の念が深く根づいており、家族たちは今も長年にわたり行方不明の親族を探し続けている。未亡人や孤児たちが中心となり行方不明者を捜索している一方、元センデロ・ルミノソのメンバーや元軍人たちもこの町に住んでいる。これらの元兵士や元反政府勢力のメンバーたちは過去の出来事についてほとんど語らず、村全体がその痛みと苦しみを沈黙の中で共有している。この地域の住民にとって、紛争の記憶とその傷は今も癒えておらず、終わりのない悲しみの中で日々を過ごしているという現実が強調されている。
現在の風景は1980年代のそれとは大きく異なる。かつて、ワリャは「赤い地域(Zona Roja)」と見なされていた。この地域は、ペルーの他の多くの共同体と同様にセンデロ・ルミノソによって占拠されていた。住民は反政府勢力に協力しなければならず、協力しない場合は命を奪われた。町の首長も、教会の鐘楼の下で頭を一発撃たれ、処刑された。1983年、軍が反撃を開始し、いくつかの反ゲリラ基地が設置された。ワリャは包囲され、容赦のない戦争が始まり、その中で何十人もの住民が永遠に姿を消した。
1983年5月13日(日)、当時9歳だったエドガー・チョックニャ(Édgar Choccña)は、父ルフィーノ・チョックニャ(Rufino Choccña)がワリャから1時間ほど離れたカナリア(Canaria)軍基地に連行されるのを目撃した。父親は他の拘留された人々と共にトラックに乗せられていた。それ以降、エドガーは父親の姿を再び見ることはなかったと語る。エドガー・チョックニャが地元の住民たちに聞いたところによると、そこには遺体が埋葬されているという。若い女性たちの中には、もし掘ったら死者の手の骨が見つかるぞとからかう者もいる。「カナリア軍基地に父は埋められた可能性が高いが、他の人々は、父がタカ(Taca)の町にある廃墟の教会で殺され、その遺体は数回に分けて鉱山の坑道に運ばれたと話している」。今日、その基地の土地は住宅地として区画整理されている。ペルー人類学フォレンジックチーム(EPAF)によると、1983年から1984年の間に、58人のフアジャの住民がカナリアで行方不明になったとされている。
チンパンパ(Chimpampa)軍基地は町のふもと、緑にあふれる広大な草原にあった。今でも高い壁が残っているのが見て取れるが、その一方で、チンパンパは穏やかな市営の苗床となっている。「ここには炉があり、向こうには礼拝堂があった。ここには高い監視塔があり、あちらでは軍が地下牢を作り、水を満たして、捕虜をそこに入れて拷問していた」と、農民のマリノ・オレ(Marino Oré)は語る。マリノは、軍が捕虜に対して行ったことを、基地の向かいにあった自宅からすべて見ていたという。カナリア(Canaria)と同様に、軍はここに疑わしいと見なした者をすべて連れてきた。16人のワリャの住民が基地の門を通り、その後姿を消した。彼らの中にはフオルナト・メンデス(Fortunato Méndez)という、フアナ・クリサンテ(Juana Crisante)の夫も含まれていた。未亡人のフアナは、彼の写真を手に持ちながら、かつての軍基地の上を歩き、オレの話に耳を傾ける。「ここには小さな草地があった、軍が射撃訓練をしていた場所だ。後にそれが墓地に変わった。昼間には土の山が現れた」と語るオレの言葉が真実なら、フアナは今、夫の遺体の上に立っている可能性がある。
ダリオ・インカ(Darío Inca)は、チンパンパで生き残った数少ない者の一人である。ネストル・バレンスエラ(Néstor Valenzuela)は、別の行方不明者の親族であり、インカの話をケチュア語で聞き、それを翻訳する。「彼は、軍に夜中に自宅から連れ出され、他の10人と共に基地に連れて行かれたと言う。目隠しをされ、脇の下まで水に満たされた穴に入れられたが、しばらくしてから引き上げられ、殴られた。8日後、彼は解放された。妻が軍に2匹のヤギを贈ったおかげで、命を助けられたのだ」と語る。インカの体の半分は震えている。歩くためには杖を使わなければならない。彼の足の不自由さは、軍に拘束されていた間に受けた暴行の結果である。ワリャで行われた学校のパレードで、町役場はインカに車椅子を贈った。それが、彼が受け取った唯一の補償である。
遺骨の上にある町
「国内には合計で6,000の隠れた墓があり、アヤクチョにはそのうち4,000がある。しかし、公共検察庁には死体の発掘を担当する法医がたった20人しかいない」と、ペルシ・ロハス(Percy Rojas)は語る。彼はペルー人類学フォレンジックチームの人類学者である。彼は「計算上、楽観的に見て、60年以内にようやく行方不明者を見つけることができるかもしれない。その間に、遺族が自分の家族を埋葬する前に死ぬ可能性が高い」と語る。
「国は行方不明者の捜索に関する方針を持っていない」と語るのは、弁護士ギセラ・オルティス(Gisela Ortiz)だ。「国は捜索すらしない。遺族は自分で、どの墓、どの谷、どの川に家族が埋められているのかを調べなければならない」と家族の状況を訴える。
ワリャで行方不明になったものたちの家族たちは、軍が彼らの家族をどこに連れて行ったのかを知っている人物がいる可能性が高いと言っている。その人物の名前はテオドミロ・ベニテス(Teodomiro Benítez)で、ワンカイノ(Huancaino)出身で、戦争後もワリャに残って暮らしている。彼はチンパンパの軍隊のトラックを運転していた。「はい、地下牢があった。そこにセンデロ・ルミノソのメンバーを入れていたんだ。拷問をしていたのかは分からない。あれは汚い戦争の時代だった。町中の道はすべて(センデロ・ルミノソの象徴である)鎌とハンマーが描かれていた。誰も信用できなかった、みんなが赤かった。毒を盛ったキャンチャやチーズを渡してきた。どれだけ多くの軍人がそれで死んだか、どれだけの爆弾を仕掛けられたか。でも、行方不明者については何も知らない。検察は何度か来て尋問したけど、僕は何も知らない。誰かを守る理由なんてない」とベニテスは言う。「ワリャの人々はあなたをどう見ているのか?」との問いにベニテスは「みんなと仲良くやっている。テロリストたちとも知り合いだ。中には広場の真ん中で立派な店を持っている者もいる」と答えた。
ルイス・シントラ監督
ルイス・シントラ(Luis Cintora)は過去10年間にわたり、ペルー、エクアドル、チリ、モンゴル、アルジェリア、ソマリアといった国々で、ドキュメンタリー制作および人権擁護プロジェクトに関わってきた。
ルイス・シントラは、ペルー国内の武力紛争における記憶と暴力をテーマにしたシリーズも制作しており、全14本のドキュメンタリーで構成されている。中でも『Te Saludan Los Cabitos』および『Minka de la memoria』は際立った作品であり、いずれも多数の国際映画祭で上映され、受賞歴を持つ。現在も、ラテンアメリカにおける人権と記憶に関するテーマでドキュメンタリー制作を継続しており、『罪なき罰のゆくえ』とともに作成されている新たな長編ドキュメンタリー映画『Un Viaje hacia nosotros』は、スペイン内戦中に亡命を余儀なくされた祖父の足跡を、俳優ペペ・ビジュエラ(Pepe Viyuela)がたどる内容である。
シントラはペルー人類学法医学チーム(Equipo Peruano de Antropología Forense:EPAF)の記憶部門、サンティアゴ・デ・チレの記憶博物館(Museo de la Memoria de Santiago de Chile)の映像部門での勤務経験もあり、またペルー国内での暴力の被害を受けた被害者団体や地域社会、さらにはエクアドルにおける行方不明者の家族の団体とも協力してきた。
監督によるコメント
ペルーの内部武力紛争における象徴的な出来事、例えばウチュラカイ(Uchuraccay)、ルカナマルカ(Lucanamarca)、アッコマルカ(Accomarca)などの事件は、報道や文学、映像作品を通じて広く知られている。しかし、ワリャというコミュニティが受けた暴力のエピソードは、一般にはほとんど知られていない。ワリャは、ペルー共産党センデロ・ルミノソがその支配を確立し、「赤い地域」または「解放区」として暴力行為が多発した最初期の地域の一つであったにもかかわらず、その記憶はほとんど語られてこなかった。本作は単なる過去の出来事の記録にとどまるものではなく、記憶を手がかりにして現在という時間を探究するものである。出来事からすでに30年以上が経過しているが、この暴力を体験した人々は今もなお、真実、正義、そして補償を求め続けている。最近では、1980年代に軍事基地が設置され、多くのワリャ住民が拘束され、拷問され、強制失踪させられた場所であるチンパパンパに、記憶の空間(espacio de memoria)が新たに開設された。また、行方不明者の家族たちは、今もなお愛する人々の行方を探し続けている。
ワリャの住民自身による人生の語りが、本作の構成を形づくり、トラウマ的な集合的記憶への没入を導く軸となり、私たちを現在という時間へと引き戻し、再び位置づけてくれる。ドキュメンタリーの中で登場人物たちは、それぞれの記憶や内面的な思索を語り、私たちは彼らの日常生活のさまざまな場面に寄り添っていく。本作ではナレーターを使用していない。一方、ドキュメンタリーに登場する人々自身が自らの記憶と現在への扉を開いてくれている。
このアプローチを通じて、私たちはロラン・バルト(Roland Barthes)やミシェル・フーコー(Michel Foucault)によって提唱された現代記号論における「作者の死」あるいは「作者の不在」という概念を実践している。ドキュメンタリーという行為自体が現実の再構成である以上、作者はメタファーとして「死ぬ」あるいは「姿を消す」べきだと考える。そのため、観客により深く、より誠実に届くためには、作者の声や制作者の存在を画面から消す必要がある。このようにして、私たちは観客自身が現実の再構築に参加する主体となることを促している。
私たちは、アヤクチョ地方のあるコミュニティにおける武力紛争とその余波を描くにあたり、証言に基づく映像言語を選択した。登場人物たちの声や語りは、オフ音声として、またカメラの前での証言として現れる。彼ら一人ひとりの語りが、ワリャで起きた出来事を再構築していく。それぞれがこのエピソードにおける自らの物語を語り、その記憶や呼び起こされる感情を共有することで、人物のより人間的な側面に焦点を当てている。
私たちは、暴力のグラフィックで露骨な描写には踏み込まない。また、憎悪やセンセーショナリズムに基づく語りを提示する意図も一切ない。むしろ、正義を求める必要性に焦点を当てており、記憶を通じて現在のポストコンフリクト(postconflicto/紛争後)の文脈に視点を移す。そして、そこでは、ワリャのコミュニティが、自らが体験した悲劇の影響をいかにして乗り越えようとしているのかが映し出される。
一方で、私たちは登場人物たちに寄り添いながら、彼らの日常のさまざまな場面——個人的な時間、労働の場面、日々の雑事、そして正義を求める活動——に同行している。この観察的アプローチは、登場人物たちを現在の文脈にしっかりと位置づけ、現実感と日常性を観客に伝えることを可能にしている。そのため、固定カメラによるショットや、被写体に密着した追跡撮影を多用している。登場人物たちの個人的な証言の断片は、作品の中で互いに挿入・融合され、現在という時代の集合的記憶というパズルを形づくっていく。
私たちの撮影(フォトグラフィー)は、登場人物の日常を探究し、現実的なアプローチを基調としながらも、ある種の詩的なニュアンスを加えることで、彼らとの距離感を近づけている。特に、登場人物のまなざし、細部、そして沈黙に重点を置いている。とはいえ、私たちは純粋に視覚的または叙情的な映像詩を作るつもりはない。むしろ、映像の美的側面と、登場人物たちの語りやトーンとの間にバランスを見出すことを目指している。私たちが目指すのは、温かく感情的な空間を作り、観客と語り手の間に、より親密なつながりを生み出すことだ。編集はリアリスティックな手法で行われ、長回しのショットや沈黙の多用によって、現実的かつ現在の場に根ざしているという感覚を強調している。
本作は、2010年に開始したアヤクチョ地方における暴力の記憶と人類学をテーマとしたドキュメンタリーシリーズに属する作品である。主な目的は、ペルー国内外の人々にペルー武力紛争の悲劇に対する感受性を高めることであり、特にアヤクチョの高地ケチュアコミュニティがこの紛争をどのように経験し、その後もその影響を受け続けているかに重点を置いている。
「歴史を忘れた民族は、それを繰り返す運命にある」という言葉を私たちは信条としている。本作は、ワリャというコミュニティの集合的記憶を生かし続ける映像装置となることを目指すと同時に、暴力事件の司法調査再開のための支援や、行方不明者の捜索・発掘作業のための道具としても機能することを意図している。
また本作は、アンデス地域や内陸部のより排除され、認められず、沈黙を強いられてきた記憶を広く伝えることも目指している。これらの地域の住民は、自身の物語が国家政策によってほとんど無視されていると感じているからである。本作は、被害者の家族や生存者が長きにわたる苦しみの中で抱えた痛みを癒し、いまだに癒えぬ傷を癒す助けとなる治療的な役割を果たすことも目指している。
他の映画作品等の情報はこちらから。
参考資料:
1. Este fue nuestro castigo
2. Hualla duerme sobre huesos
作品情報:
名前: 罪なき罰のゆくえ(Este fue nuestro castigo)
監督: Luis Cintora
脚本: Luis Cintora
制作国: ペルー
製作会社: Coproducción Perú-España、AV2Media Films
時間: 88分
ジャンル: ドキュメンタリー、ドラマ
※日本語字幕あり

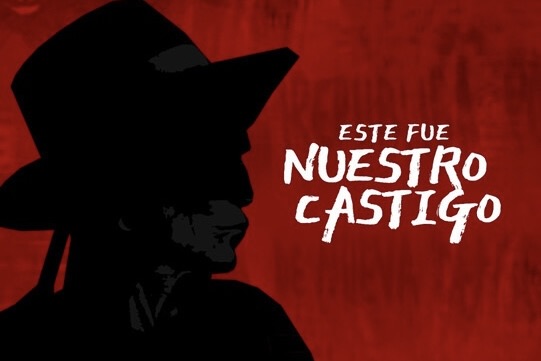
No Comments